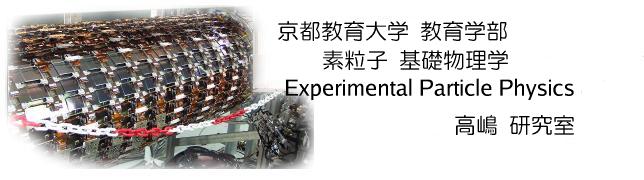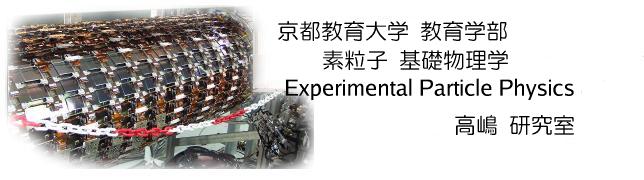
高嶋研究室の目次
高嶋研究室Wikiページ
高嶋研究室の研究内容
卒論、修論について
高嶋の研究関係
研究室ニュース
担当授業の情報
研究室の計算機
物質物理関係
リンク集
大学改革関連
高嶋研究室の研究内容
卒論、修論
- H19年度の卒論>
- H18年度の修士論文
- H16年度の卒論
- H15年度の修士論文
- H15年度の卒論
- 新免許法。最初の新免許法の学生。この年度
は0名。
- H14年度の6c6c卒論
- KOPIO実験のためのα線源を用いた Nitrogen Scintillation の
研究 村山 芳幸
- オブジェクト指向技術を利用したシミュレーターの研究 山田洋平
- H13年度の卒論
- H12年度の卒論
いままでの卒論生のページ
6c6c6c
高嶋の研究関係
- CTB2004 picture、Atlas 測定器の絵
- 2002年浜松でmodule production開始
- アトラス実験のreal movie 10。でもproducerBasicなので最大34kbpsの性能しかでない。ビデオテープをAopen VA1000Max-NT1で取込み(mpeg2)、linuxのmencoderでmpeg4のaviに変換、producerBasicでreal movieにした。やっぱりprouducerをかわないとlinuxでみれない。
- athena のインストール
- SCT関係のプログラムの動作を7.3.0で
- Athena atlrel_5のジオメトリーのシリコン
検出器のVRMLファイル,300kbyte,解凍後(gunzip)7Mbyte、VRMLファイルビューアー,2Mbyte,解凍後5Mbyte
インテルベースRedHat7.2,7.3で動作確
認済。CPUは2.5GHz,メモリーは500Mbyteなら問題なし。500MHz,128Mbyteでは
かなりのストレスあり。左ボタンで物体回転、真中で物体引き寄せ押し出し、右ボタンで物体移
動。物体モデリングにだいぶ時間がか6cかる。ピクセル、TRT、カロリメーター、
ミュオンもそのうち載せます。
-
ATLAS(周長27キロの超電導衝突加速器LHCでの実験)
-
アトラス日本グループ
ス研究会
- 検出器の各部分の状況
- 建設の様子
- PC LinuxでGPIBやRS232Cを制御するには。そのHow toへのリンク
-
シリコン検出器の開発:片面読みだしで低温で運転すれば放射線に強い
-
新しい物理が期待できる?
-
新しい検出器テクノロジー 40MHzで発生する事象の区別 Binary or Analog
- CDFのpublication link
- 3年ぶりにCDFのシフトをした。CDF関連のファイルをあちこち拾い読み。大学院生のシフト(エース)半導体検出器訓練ファイル(23Mb)
- 浜松ホトニクスでの1/4ラダー組み立ての写真
- 温度IC LM35DZを秋月電子より購入、IOカードDACカードをWebtronixより購入(burnin用)
- flex hybrid データとPawのマクロファイル
- flex hybrid schematic,pict file for Mac Canvas,stimulas system pedestal,stimulas system gain scan
- burn-in system を教育大学でテストした。xtlがうまく動く。浜松へ送った。
- flex hybridのレポート(PS)flex hybrid testing, jlatex fileflex testing in jlatex
- flex hybrid testing picture
- test standを動かしています。port cardの信号をlogic analyzerで調べています。
-
lepton+Bs->DsPiは見えないことがわかった。VAXのトップ解析コードをIndyに移植
-
CDFのシフトを取りました
-
'95 KEK
Beam test using SVXII readout system
-
SVXIItest
standによるレーザーテスト
-
UNIXマシンからのGPIBによる計測機器の制御
KOPIO(K0->Pi0NuNubar)
- ストローチューブのGeant4シミュレーションはここ。
理科教育関係
今までの研究内容の概略(ポストスクリプト)
今までの研究内容の概略(PDF)
スケジュール2002
- 7月26日:SCTソフトエア第1回会合
- 9月15日ー9月20日:KOPIO ビームテスト
- 10月25日ー10月27日:ATLASソフトウエアワークショップ、SCTソフトエア第2回会合
- 12月6日ー12月7日:SCTソフトエア第3回会合@岡山大学
- 12月8日ー12月18日:CERN
- 12月23日ー12月26日:ATLAS 総会、C++ 勉強会、MWPC作成
スケジュール2001
- 7月4日ー7月14日:CERN
- 8月19日ー9月9日:フェルミ研究所
スケジュール2000
- 9月16日ー10月5日:CDF エンジニアリングラン
- 12月4日ー12月7日:アトラスSCTビームテスト
- 12月19日ー12月22日:GEANT4講習会
- 12月27日ー12月28日:アトラスjapan総会@神戸
研究室ニュース
- 研究室なんでもNOTE(閲覧のみ)
- Pikiwikiページを開設しました。
- Geant4 3.0をつかってストローチューブと中性子の反応をシミュレートするプログラムを作った。(01/1/17)
- CDF RunII software 3.11.0を使っている。SoftRelToolでモジュールを書き換えて使う練習中。まだ kerberos ができない。(01/2/7)
- 両面印刷付LBP730をマイコンショップ川口より購入。トナーをつけて6万8千円。 Linuxのマシンにつけてプリントサーバーにしようとしたら sambaが動かない。メーリングリストを検索して解答を見つけた。/etc/hostsに問題あり。127.0.0.1 localhost.localdomain localhost buat2を127.0.0.1 localhost.localdomain localhostにしたらなおった。あほみたい。 vine 2.0 のlpdでは/etc/hosts.lpdにクライアントのホスト名を書く必要がある。また、/etc/smb.confのprintersにgest ok = yesと書いておかないとアカウント名smbのパスワードを聞かれてつまってしまう。これでプリントサーバーとしての設定はOKとなった。
- CDF RUNII softwareをatx4にインストールした(frozen 3.60)。 executable を作るには6ギガバイトcdfsoftアカウントに必要になる。実行時にはオラクルサーバーへのアクセスを外して行なう。(00/8/24)
- fire wallのなかにいると京都教育大学ではLinux Machineでリストサーバーを動かすことができなくなるようだ。majordomoはいれてみたけどだめだった。majordomと8文字にuser IDがなることが落しあな。(99/10/21)
- 研究室の100V電源に200Vが半日かかった。ATXパソコンEWS4800など5Vスイッチ式の電源はみんな壊れた。hub、ACアダプターも全部壊れた。もう悲惨。(99/10/21)
- /var/log/secureをみたらまたアタックしてきたようだ。imapdを起動させようとしたようだ。これでトロイの木馬プログラムを送りつけ、パスワードファイルを盗んで、rootの暗号化した部分を解読したみたい。Vine Linuxはもうimapdがなかった。pwconvでシャドウパスワードにしてあるので、暗号化したパスワードファイルも読めなくなっている。ひと安心だ。(99/7/13)
- Vine Linuxをプラットホームの通信販売で買った。これを研究室のサーバーにインストールした。セキュリティを強化するために/etc/hosts.allowというファイルにALL: ALL: DENYを入れたらrootに入れなくなってしまった。皆さんもセキュリティの強化し過ぎに注意しましょう。もう一度入れ直しました。(99/7/12)
- 研究室のRedHat5.1のLinuxマシンのパスワードが3月に続いて7月にもとられました。ログを消した後ごていねいにいつやったかということまで教えてくれました。変なアカウントをたくさん作っていきます。(99/7/6)その後最悪。そのアカウントを消そうとしたら/に設定してあったのでファイルが消されはじめた。すぐ落せば良かったのに呆然としてたらまず/homeがなくなって/usrの一部が消えてしまっていた。もう最初から入れ直すしかない。(99/7/6)
- 教育大学はスチーム暖房なので湿度が低い(30%)。皆さん部屋を加湿しましょう。最適は40-60%です。(99/1/29)
- 理科教育と自然科学の論文集の創刊決定。ポイントはpdfを使うこと。しかしpdfファイルをたばねてヘッダー、フッターをつけるソフトが見つからなくて困っています。(99/1/29)
- 4月30日SVX3チップテストボードをピン一つずらして差して、スクランブルカードのヒューズを切ってしまった。幸い何も壊れなかった。感謝。
-
被曝の大きなn-in-n detector 安定に動作@150V -20度の低温で 冷却も大事だが断熱も大事
p-in-n OK no surprise
-
netscapeのソースコードが公開されました。linuxから日本語入力できる日も近い
-
natsci hard disk crashed 音の出るのはクラッシュする
-
高嶋研に4台のEWS4800, network connection OK. 後はソフトを入れるだけ
-
natsciに日本語入力できるnetscape comunicatorをインストールした。ページも直接書き換えられます。
担当授業の情報
-
学部の授業
- 授業の道具
- gnuplotのdemonstration、
実行するときは解凍した後、gnuplot; load 'simple.dem'
- rootではroot; .X xxx.C ; .q で終了。
- 物理学実験III
- 電磁気基礎:
- 便利なプログラム
- MuPADを使っ
て勉強しよう。そのうちMuPAD,JAVAが入ったパソコンが売り出されるぞ。
Linuxなら
manualというコマンドでtexで書いたみたいなハイパーヘルプファイルが見れる。
- アトラス実験のものすごい強さの磁
場(山下作)。中心ソレノイドが2テスラあることを考えると空芯トロイドの部分が
とても強いことが分かる。CMS(Compact Muon Solenoid)検出器の場合、ミュー
オンは鉄の中で運動量解析される。分極磁荷と言う考え方はこのときあまり
適当でないことが分かる(向きが逆になる)。ボーアマグネトンを微小周回電流と考えその合成によって、周回大電流が
生まれているように考える方が良い。
- 鉄釘の成分はC:0.16,Si:0.22,Mn:0.57 (wt%)
- 物質がないところでの発散はHもBもゼロだが、発散がゼロということは
場がどこまでもできて行くということ。空間が広がって行くので強度が下が
るだけ。光が質量ゼロでどこまでもとどくのと同じ起源。
- 物質科学II:講義資料
-
物質科学概論:’やさしい素粒子物理学’ということで2回講義しています。
-
物理学:教育学部の共通科目で簡単な実験を行なって物理の面白さを知ってもらう授業です。液体窒素に風船をつけるとか、手の上に鉄ブロックをおいて金槌で叩いてみるとかは、オリジナリティのある実験です。'Why
does this universe look like this?'を基本テーマとしてやっています。
- 力学関係
- 宇宙論のTL10D Star Suite 7 file、フォントの標準
をMS ゴシックのままにしてたのが良くなかった。ただのゴシック
のほうがOpen Officeと互換性をとりやすいか。創英角ポップはよさ
そう。
- 物質、熱力学関係
- 液体窒素を使うとき、大きなガラスのデュワー瓶があったので使っていた
が、1kgとって使っていると、突然破裂した。島津カタログなどでは
全てステンレス容器を使っている。傾けるときに大きなストレスがか
かるのでやはりステンレスでないといけない。
- 物質が結びつく力には共有結合、イオン結合、配位結合、水素結
合がある。配位結合の例としてはヘ
モグロビン、ミオグロビン、クロロ
フィルがある。rasmol(win98)で見てみよう。colours menuからgroupを
選択しヘム基を探してみる。
- 原子物理関係
- ガイガーカウンターでX線を計数し、自然現象の統計性を学ぶ。
- 10秒間の計数を100回行い、頻度分布を作成する。これと
ポアッソん分布の理論式と比較を行う。
- エクセル、OpenOfficeのテンプレートファイル。
- 5章、素粒子の世界のPPTファイル
- 物理学II:物理の公式は覚えるものでなく導くもの。導くには数学が必要。
- 講義のプリント
- ベクトル場の考え方を身につける。 こ
の図を磁場と考えるとベクトルの大きさがr倍に示されているので注意する。
- 梅雨の季節は密閉型の箔検電器でないと箔が開かない。静電誘導の説明が
できなくなる。
- java (お勧めは 独習JAVA ジョゼフ オニール、SE Shoeisya) ダブル バッ
ファリングはMozillaで見えなくなった。Mozillaプラグインは動かないことも
ある。appletviewerで我慢するのが無難。
-
小学校専門理科:4人ずつ8班でやる実験ということでやっています。
- 一回めは鉛筆の芯の電気
抵抗を計る実験です。(来年は、電源を購入し、接続穴付きバナナ端子を
使う予定)
- 2回目は釘の磁化と導線の
回りにできる磁場。強磁性体の鉄は成分によって透磁率がことなる。いろいろまとめてあ
るペー
ジ。、鉄釘の成分はC:0.16,Si:0.22,Mn:0.57 (wt%)
- 3回目はコイルでできる磁
界とモーターの作成です。右ネジの法則について勉強します。
- 基礎セミナー:毎回20分の発表を3人行なう。高嶋の発表は遺伝子の構造、配列の決め方。
-
高校での授業
-
大学院の授業
-
素粒子物理学特論:基本的な物質の性質はすべての自然現象の基礎となる。自
然に対する基本的な理解がどこまで到達しているかを考える。
-
物理学特別演習:自然を探求する手段として、粒子検出器や、電子回路、計算機の知識が必要になる。それらについて基本的な演習を行なう。
-
理科教材特別演習:計算機と物理学
- もう終った授業科目
-
量子力学 :量子力学は、定常状態や具体的な波動関数の表示について学ぶ。さらに、スピン状態を記述するために行列を使うことを最初に学ぶ。この後行列力学の一般的な例として角運動量演算子の表現を勉強する。具体例を JAVAなどを使って示す。
- 平成11年度計算機実験テキスト
- 平成10年度計算機実験テキストを読むにはAcrobat Readerが必要です。psのテキストはこちらです。
-
平成9年計算機実験
-
平成8年計算機実験:テキストを読むにはAcrobat Readerが必要です。ところで、今年からJavaという言語に取り組もうと思います。
研究室の計算機
- パソコン工房アンフィスバリュー2530GE: RedHat8.0 パーソナルを入れ
た。グラフィックスも intel845GEに入っている。インストーラーではi810の
デバイスドラーバーを使用することになる。それでは画面がおかしくなったり
する。そこで/etc/X11/XF86ConfigのSection "Device"のDriverを"vesa"とす
る。更にBIOSのAdvanced chipset featuresのInternal Graphics Select を
8MBにするとよい。でないとredhat-config-xfree86を使っても640x480のまま。
VRAMサイズはwin2000もBIOSともに64MBになっている。www.xfree86.orgや
support.intel.com, mailing list archiveを参照のこと。
しかしこの後、ログアウトすると画面が黒くなることが分かった。また
"Device"のDriverを"i810"に戻してやると正常になった。結局BIOSの値を
変える方が重要だったようだ。XFREE86 4.3で改善されることを期待する。
- DELL inspiron2650のディスクをPartionMagic7.0で分割のあと、
Laser5Linux7.2expをいれた。テキストインストールでないと駄目。
Xconfiguratorをすると動かないドライバーを入れた挙げ句、run levelが5に
なり常に画面が流れてしまうので注意する。こうなったら/etc/inittabをめく
らで書き直す。正しい方法はここ
にあります。ただしここに載っている/etc/X11/XF86Config-4はほぼよいが液
晶のパラメータが合わないので、そこだげgeneric laptopのものにする。
kernel source rpmはバイナリの2枚目にある。
- 松下Let's note CF-M1をじゃんPARAで9万円で買った。Defrag、Fipsして
Laser5 7.2expをいれた。とてもらく。自宅でADSL接続を試みる。そのままで
は動かず。www.roaringpenguine.comからGUIつきのSRPMをダウンロードして
RPMにbuildしていれたら、98のような設定ウィザードが動いた後、tkpppoeで
どのアカウントからも接続できるようになった。(02/5/21)
- 雑誌付録のRedHat7.2,Caldera,Holon3.0製品版、Laser 5 7.2exp製品版,
Vine2.5製品版を研究室のパソコンにインストールしてテストした。AbiWordの日
本語対応のものは無かった。フォントがきれいなのはGnomeのほう。(02/5/21)
- sharp mebius PC-FJ140M(all in one handy note,XGA,64M,12G)にVine 2.0 linuxをインストールした。defragで準備してからfipsで半分にした。ATI RAGE Mobility M はグラフィックインストールができない。テキストでインストールした後、ゆっくりXをインストールする。どうしようもないときはCtl+Alt+Del でHDをSyncしてから電源キーを4秒押して電源を切る。(?)XFree86-SVGA-3.3.6xxx.i386.rpmをインストールする。その後Xconfigurator --server SVGAを実行して、SVGA serverの利用を宣言して/etc/X11/XF86Configを生成する。色は16bit。うまくいかないとかエラーが出るが、気にせずstartx.確認後に/etc/inittabを編集して、Xのセレクタが出るようにできる。planexのネットワークカードENW3502-Tはホームページのように/etc/sysconfig/pcmciaの中をPCMCIA=yes PCIC=i82365として設定できる。後はnetcfgでパラメータを入れる。(00/9/2)
- Geant4 をコンパイルするためにLaser5 6.0rel2を2台のLinux machineにインストールした。コレガのLANカード(via-rhine)が登録されている。コンパイルはできる。フェルミ研cdfのソフトがインストールできないのは逆参照できないからなのか?(00/4/11)
- IndyをIndyZoneから5万円で購入。やっとIRIX6.2になった。(00/4/11)
- 200V事件でNEC EWS4800の電源が壊れてしまったので、代替品としてATXを3台もらった。何故かWindowsNTが入らない。(FDのせいと判明)そこで最初の一台にはFermi Linux(RedHat5.2base)をいれた。マシンの仕様は以下の通り。Mother Board:ABIT BH6, CPU:Intel Celeron400, HD: ST-38421A, Video Card:Xpert98(ATI Rage pro AGP), CDROM:Aopen CD-940E, keyBord:日本語Win98用, Network card:corega FastEther II PCI-TX... AGPはうまくいかないように見えてstartxで動いてしまう。corega FastEther II PCI-TXはホームページ(www.corega.co.jp)の解説のやり方で設定した。/etc/conf.modulesに alias eth0 via-rhineと書いた。その後、control-panelのnetworkの設定のところを使った。EWS4800の20inchi displayは垂直同期信号周波数が60Hz,70Hzなので30HzのVGAモードが駄目。別のdisplayを使った後60HzでWindowsNT,XFree86ともにうまくいった。 Network cardとしてはplanexのENW-8300-TがNE2000互換PCIなので手間いらずだった。これは他のCerelon Machineにいれてある。(99/11/12)
- libretto20:2年半前にあまりの小ささにびっくりして7万円で買った。最近(1999.4.26)少しアップグレードした。4.3GのHDをDOS/Vパラダイスで2万円で購入。ニノミヤ電気でFDDを1万6千円、チチブ電気から4千円で12Mメモリーを買った。PCcardはIOデータのPCLA/Tで2年前にOAシステムプラザで買ったもの。まず、windows95をフロッピーにバックアップした。Liux JapanのCDを使ってdebian2.1をインストール中。いまのところネットワーク接続まで到達した。あとはNFSでソフトをインストールしてXを動かせば出来上がりとなるはずです。皆さんもサブノートにLinuxを入れましょう。->Xが入りました。LinuxJapan第3号の記事を見てやっています。(99/5/10)
-
Indy(R5000):Netscape4.05はシステムパッチ1710も当てたので日本語入力できる。SVX3チップのテストシステムの開発に使っている。トップクォークの質量の計算、ボトムの崩壊モードの探索に使用している。JDK1.1も入れてある。-->System HDがクラッシュした。手持ちの2GbHDをいれた。/usrを書き換えたくないのでシステムはcdromから入れ直した。入れ直しの途中でリセットしてしまい、少し変なところがある。(99/10/x)
-
SUN IPX:かなり前から使っている。出来れば、基板をアップグレードしたい。マウスが壊れたので秋葉原まで買いにいく予定。->(3000円)
-
VAX3100:SVX Chipを使ったシリコンセンサーの読みだし回路を動かすために使っている機械。
-
PowerMac6100/60AV:電子メールを読んだり簡単な文書の作成に使っている。CU-SeeMeで研究の情報交換に利用している。
-
PowerBook520c:4年前に買ったもの。今は家で家族が使っている。最近32Mbメモリ(1.8万OAシステムプラザ)を入れた。分解方法は、裏のまん中2箇所の螺を外して、キーボードをとり、CPUの入った金属性の蓋を持ち上げながら(外れない)メモリーを押しているプラスチックの部品を止めている金属のタブをペンチで曲げてとり出すという、恐ろしいやり方をとった。金属のタブは曲がったままで元に戻らなかった。電源を入れると立ち上がるまで3回リセットしたが、接触が回復したのかその後は問題なくなった。(99/5/8)
-
DOS/V(ATX):基板が安かったので衝動買いした後、衝動的に部品を買って作った。ビデオボードがS3-ViRGEを使っているのでまだLinuxは入れていない。ー>Linuxをいれました。ビデオボードはS3-trioV64+にしました。最初にWindowsをいれたため、ディスクのBIOSパラメータを変える元気がなくなってしまった。LILOがうまくいかないのでDOS領域にカーネルを入れてブートしている。Slackwareを使ってインストールしました。ー>ハードディスクが壊れたのでRedhat5.1をインストールしてある。高エネルギのネットワークのネームサーバーにしている。(99/1/29)
-
AT : 理学科のサーバーとして組み立てた。マザーボードはASUS P/I-P55T2P4,CPUはAMD133MHz,SCSI
Tekram DC390,HD WD1.2Gbyteと標準的なものを使っています。RedHat4.0を使ってインストールしました。ビデオボードはS3-ViRGEです。苦労したのはマウスの設定でした。logitech
MauseManのばら売りを買ってシリアルポートにつけました。ボタンが三つあるにも関わらずChordMiddleパラメータをnoにするというのがポイントです。そうしないとghostviewなどでとんでもないことになります。左ボタンと真中ボタンを同時に押すことになり、zoom
windowが限りなくできてパニックになります。samba,netatalkを動かしてサーバーとして機能するようにしてあります。これについて書いたサーバーシステムの構築を読むにはghostviewが必要です。サーバーシステムの構築がAcrobat
Readerで読めるはず?Web serverのCGIを使った機能拡張(ps,pdf)というレポートを今書いているところです。samba1.9でwin98に対応していないことが判明。要バージョンアップ。
物質物理関係
リンク集
理学科のページへ
大学改革